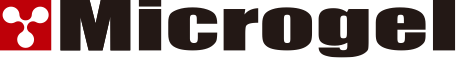【保存版】産業工場様向け悪臭苦情対策
悪臭の原因と解決策を徹底解説!
工場での悪臭苦情対策はニオイの種類や周辺環境により様々。
日本の悪臭問題に関する国家資格である臭気判定士保持者の私が法律や原因調査、解決方法まで
一挙ご紹介致します!
突然、行政や周辺住民からの悪臭クレームのご連絡。どのように対応したら良いでしょう。
ニオイの苦情に対する知見が無く、どうしたら良いのか、早く解決したいけどそもそもニオイって何?
法律の規制はあるの?どうやって評価するの?
ここでは悪臭苦情とどう向き合えば良いのか
必要な知識から対策方法まで弊社の経験を踏まえてご紹介したいと思います。

目次
1. 悪臭苦情のメカニズム

悪臭は大抵の場合、排気ダクトや煙突から排出された臭気ガスが工場周辺に飛散する事で発生します。
ここで大事な事は、工場周辺の生活環境エリアにおいて"着地した時"の臭気の強さが苦情レベルかどうか、という点です。
排出された臭気ガスは大気により希釈されながら着地しますのでその着地した時のニオイの強さがどうかという点が悪臭リスクの管理にはとても重要です。
2. 排出された臭気の行方

煙突から排出された臭気は風に乗って風下へ飛んでいきます。臭気苦情の発生頻度が常時でない点はこの風向きが大きな要因です。
特に苦情発生に季節性がある場合も季節風の影響が大きいです。
また、悪臭苦情は周辺住民の方々の生活環境に密接に関わっています。弊社で頂くお問合せの中で最も多い時期が春先から夏前までです。
これは季節的に暖かくなり、人々が住宅の窓を開けだすタイミングと一致します。
概ねこの時期に頂くお問合せはその年の冬までに対策を完了させ、翌年の春に備えます。
3. 臭気対策に要する時間

弊社の実績ベースでお話させて頂くと、お問合せを頂いてから対策完了までで平均して約1年~1年半ぐらいです。
えっ、そんなにかかるの?と思う方もいらっしゃるかも知れませんが、弊社でお問合せ頂く際は矢継ぎ早に対策装置を提案する事はありません。
対策装置も安価な投資ではありませんから臭気の専門家がしっかりと原因調査を行った上で可能な限り必要最低限の対策を検討しご提案をさせて頂いています。
これは過剰投資や能力不十分による問題の未解決を未然に防ぐ為に必要な事だからです。
4. 悪臭の法律について

昨今環境に対する意識の向上を背景として環境問題に関しては様々な法律や規制が定められていますが、
悪臭にもそういったものは存在するのでしょうか?
下記に現行の法律に関して解説していきます。(2020年4月現在のものです)
- >>>目次へ戻る
- >>>目次へ戻る
- >>>目次へ戻る
- >>>目次へ戻る
- >>>目次へ戻る
- >>>目次へ戻る
- >>>目次へ戻る
- >>>目次へ戻る
- >>>目次へ戻る
- >>>目次へ戻る
- >>>目次へ戻る
- >>>目次へ戻る
- >>>目次へ戻る
- >>>目次へ戻る
- >>>目次へ戻る
- >>>目次へ戻る
4-1. 悪臭に法的な規制、基準はあるの?
悪臭については国が定める悪臭防止法という法律があります。
悪臭防止法では、一部例外を除き、悪臭を排出する全ての事業所が対象となります。
規制方法については国が悪臭防止法として定めている規制の他に各地方自治体が独自で定めているものもあり、地方自治体独自で規制を定めている場合、そちらに準ずる必要があります。
現在の法律では臭気の排出規制及び敷地境界線での管理濃度の基準値として臭気指数による規制基準と特定悪臭22物質の各単ガス濃度で規制基準を設ける2通りの方法があり、
どちらか一方もしくは両方とも遵守する事が求められています。
どちらを遵守すべきなのかは自治体により異なりすので悪臭苦情が発生した場合、まずはご自身の事業所がどのような規制方法となっているのかを各行政のホームページ等でお調べ頂いた方が良いでしょう。
4-2. 規制がかかる場所
悪臭防止法で規制対象となるのは下記の3箇所です

少々ややこしいですが、下記リンクの1ページ目にわかりやすく記載があります。
出典:環境省水・大気環境局大気生活環境室/平成28年度
規制の厳しさは用途地域により異なります。
悪臭の規制値を知る為には事業所の用途地域(工業、準工業、住居区域など)をお調べする必要があります。


4-3. 臭気指数規制と特定悪臭物質規制とは?
悪臭の規制方法には①臭気指数による規制と②特定悪臭物質の単ガス濃度を用いた規制基準の2パターンがあります。
①臭気指数は人間の鼻を用いてニオイを定量化し、その数値で基準を定める方法です。
複合ガスであるニオイを人の感覚の違いも加味して定量化する事ができるので実際の影響度に近い評価を行う事ができる方法と言われています。
②特定悪臭22物質は悪臭原因の代表物質を22物質ピックアップしてそれぞれの物質濃度により規制を掛けます。
人間の鼻で感じる事ができるニオイ物質は40万種類と言われています。
その中の22物質をピックアップしても中々現実の影響度に反映させる事が難しい為、臭気指数という概念が生まれました。その為臭気指数の方が比較的新しい概念となり、昨今の規制方法としてだんだんと臭気指数規制に切り替わっています。



4-4. 排出口での規制について

何やらややこしそうな悪臭2号規制。
敷地境界は規制値がいくつと定められているし、排出水は敷地境界の基準値+16と非常に明快なのに対して排出口規制はシミュレーションや排ガス流量計算と複雑な印象を受けます。
大事なのは敷地境界線の基準を守る為の排出口規制であるという事。
臭気が大気解放後に薄まりながら飛んでいくことを考慮すると排出口から敷地境界までの距離や排出口の高さなどを考慮して、希釈された後に敷地境界線で着地する臭気濃度=臭気指数が敷地境界線での基準(1号基準)に適合しているかどうかという判断になります。
その為、排出口基準はその時の状況によって変わるのです。ここが理解を難しくする点と思います。
シミュレーションや排ガス流量計算に用いられる計算項目はざっと風量、排出ガスの排出速度、排出口高さ、排出口の口径、排出口の向き(上or横)、周辺最大建物高さ、排気温度、水分量、排出口や建屋から敷地境界までの距離等です。
ざっとご紹介しましたが、臭気指数規制と特定悪臭22物質では用いる計算項目が異なりますのでまずどっちで規制が掛かっているのか、また、規制基準の設け方についても様々ありますのでまずは自治体にお問合せ頂き、お調べ頂く所からスタートすべきと思います。
臭気指数はシミュレーションソフト、特定悪臭物質は手計算という事を覚えて頂ければと思います。
下記にそれぞれリンクを貼っておきますのでご参照下さい。
ソフトをダウンロード頂き必要項目入力すると2号基準が自動計算されます。

↑この条件での排出口での規制値(2号基準)は臭気指数28(臭気濃度630)となります。
これ以外のパターンもありますので各事業場の排出条件に沿って入力、計算してみて下さい。
出典:つくば市ホームページ
残念ながら手計算です。計算方法に沿って計算すると22個の悪臭物質それぞれに対して何ppmという基準値が算出されます。
4-5. 悪臭規制の注意点
上で述べた通り悪臭の規制基準には敷地境界(1号規制)と排出口(2号規制)、排出水(3号規制)の3つの規制があります。
弊社でお問合せ頂くケースとして排出水の方で苦情になるケースは非常に稀ですので、敷地境界と排出口を主に解説します。
規制基準は臭気指数でも特定悪臭22物質でも敷地境界線や排出口でいくつという数値で規制が設けられています。
特定悪臭22物質は上でも書きましたが、人間の鼻で感じる事ができる物質は40万種類あり、その中の22個をピックアップして規制を設けても現実を反映しきれない事が多々あるので昨今ではより現実的な評価ができる臭気指数規制になっていますよと書きました。
では、臭気指数規制も完璧か、と言われればそうではないのが現実です。
えー、規制基準守ってるのに苦情続くの?という事は正直あります。
悪臭の影響度合いは場所や環境、排出条件により様々なので一概にいくつと規制を設けるのは難しいのです。
これは仕方ない事と思います。より悪臭の影響度を簡単に細かく評価できる技術(スパコン並みの流体計算が各自でできる且つちゃんとエビデンスもある)があればもっと現実を反映できるでしょうが、現状では難しいです。
ただ、特定悪臭22物質の頃(1970年頃)からほぼ手探り的に悪臭公害に取組み、臭気指数として規制基準を設けるまでの道のりについては大変な苦労があったと思います。
いきなりニオイを数値化して規制をと言ってもかなり難しい事です。
私たちの生活環境の保全に尽力頂いた方々へ私個人としてはそこに敬意を払いたい気持ちです。
悪臭規制は現実をカバーしきれない事から守るべき一つの基準ではありますが、法的な数値を守るだけでは必ずしも悪臭苦情を抑制するには不十分なケースがあり、自主的な改善努力も必要な事をご理解頂き対策に臨まれた方がよいでしょう。
臭気の強さについて ~ニオイの評価方法と影響度~


(脱臭効率70%を想定)

(脱臭効率90%を想定)
5-1. 臭気の強さを表す臭気指数と臭気濃度とは?
臭気苦情の難しい点はニオイの感じ方は人それぞれという点です。悪臭公害は感覚公害と言われ、人により感じ方が異なるのです。
その顕著な例として産業工場の現場で働く人と周辺住民の方々とでは感じ方に大きな差があり臭気影響の強さを実感できない事が多いです。
ではニオイはどうやって数値化すべきでしょうか?
その答えは統計です。統計処理を用いればバラツキのある感覚強度を補正し、一つの値として出力する事が可能であり、その統計処理された結果がニオイのものさしである臭気指数や臭気濃度となります。
臭気指数は人の鼻を使った測量方法で現在の技術の中で最も人間の感覚に近い尺度でニオイを定量化する事が可能な方法です。
臭気指数や臭気濃度を測る作業を『嗅覚測定(三点比較式臭袋(においぶくろ)法)』と言います。
この嗅覚測定の方法はサンプリングした臭気を無臭空気で薄めていき、何倍に希釈したらわからなくなるか、という事を6名の鼻を使って測定します。この時の希釈倍率が臭気濃度となります。単位はありません。
なぜ6名なのかという点については複雑な統計の知識が必要となりますのでここでは割愛させて頂きます。
臭気指数は臭気濃度に対して常用対数をかける事で算出され、臭気指数の方がより人間の感覚に近い数字を求めたものとご理解頂ければと思います。
~臭気指数の求め方~
臭気指数=10×log(臭気濃度)
例)臭気濃度1,000の場合
log(10)1,000×10=30(臭気指数)

上の表を見て頂ければわかると思いますが、指数が10増えると臭気濃度が10倍になります。
臭気濃度は測定者の閾値(わからなくなるまで希釈した時の希釈倍率)により求められますので
一つの位に対して10個のみです。
例えば臭気濃度32,000に相当する臭気指数は45となります。仕組みがわかればとても簡単ですね。


5-2. 悪臭の影響度について知る~クサイ=影響度が強いではない!?~
臭気の影響度を知る上でとても重要な内容です。
皆さんは『ニオイがとてつもなく強くてけど排気風量の少ないダクト』と『ニオイの強さはそうでもないけど排気風量が大きい煙突』ではどちらが周辺へ影響度が大きいと思いますか?
答えは「一概にはわかりません」です。なんだよ!って思うかも知れませんが、ここが結構ひっかけなんです。
よく工場へ現場確認に行くと、とてつもなく強いニオイが出ている小さな配管等をご案内頂く事が多々ありますが、
ニオイが強い=影響度が大きいでは無いという理解が必要です。
臭気の影響度は単に排出されるニオイの強さだけではなく、排気風量も大きく関わります。
これはO.E.R(odor Emisson Rate)と呼ばれ日本語では臭気排出強度と言います。
O.E.Rの求め方は臭気濃度×排気風量(m3/h)です。
この数字が大きければ大きいほど周辺への影響度が高いと言えます。
つまり、排気の臭いはとてつもなく臭いけど風量の小さい排気と臭いはそこまで強く無くても大風量の排気があれば周辺影響は後者の方が強い場合があるという事であり、排気の臭いが強烈だからと言って一概にそこが原因でない場合も多いです。


表に纏めて順位付けをしています
臭気拡散シミュレーション

ニオイは目に見えません。そこが、この悪臭問題の解決をより難しくしているのだと思います。
拡散シミュレーションは目に見えないニオイを可視化する作業です。弊社で臭気対策をご提案する際は必ずと言っていいほど実施します。
ニオイを可視化する事で周辺への影響範囲と拡散後の濃度(ニオイの強さ)がわかりますので対象エリアの着地濃度からどこをどの程度低減させる必要があるのかを逆算し、対策に向け具体的な検討を行う事が可能である為、必要最低限の対策を行う近道と言えます。
各排気の風量、臭気濃度、温度、湿度、排気口の高さや周辺建屋条件などを入力し、計算を行う事で、排出された臭気が周辺へどのように飛散するかをコンピュータ―でシミュレーションし、対策案や対策装置のご提案を行っています。弊社で行う拡散シミュレーションは、規制基準を算出する時に用いるシミュレーションソフトよりも複雑な条件を反映できるものを用いています。
シミュレーションに用いる計算条件は弊社で測定を行う事が多く、この測定作業を弊社では『臭気対策アセスメント』と呼んでいます。
臭気対策アセスメントに要する日数は中~大規模の工場様で3、4日程の作業となります。
悪臭苦情解決までの道のり
弊社で悪臭苦情を解決する場合の一般的な手順について下記にご紹介します。
現地状況の確認など
(現地臭気測定)

スプレーデモテスト
STEP1 原因箇所の絞り込み
苦情原因と思われる箇所を絞り込みましょう。苦情発生エリアとある程度距離が離れている場合、複数の排気ダクトや煙突が原因である事が多いです。
周辺住宅との距離が近い場合、建屋からの漏洩や解放型の廃棄物置場、排水処理施設等も原因である場合があります。
大抵の場合、工場様側である程度絞り込んで頂いたものを後日弊社専門員が現地へ確認に伺い、
対象箇所の擦り合わせを行います。


STEP2 臭気調査~臭気対策アセスメント~
絞り込みが完了した臭気発生箇所について測定調査を行います。
基本的には特定した発生源全てにおいて風量、温度や臭気濃度等の測定を行います。
排出される臭気の強さに変動がある場合には各箇所2、3回臭気測定を行う場合もあります。
仮に対象となる箇所が10箇所であれば各3回測定した場合臭気サンプルを30検体採取し、臭気濃度(臭気指数)測定を行います。
これはリスクの最大値を把握する為です。
この作業の目安としては中、大規模の工場でだいたい3~4日程度です。

STEP3 臭気拡散シミュレーション
STEP2での調査結果をシミュレーションに落とし込みます。STEP2はいわばこの拡散シミュレーションを行う為の調査といっても過言ではありません。
出力される拡散計算結果を基に対策案を検討し、最適な対策方法を検討し、ご提案します。
この方策の中には単に脱臭装置を設置するだけでは無く、排気ダクトの排出条件(ダクトの向き、排出スピード)変更等も含まれます。
悪臭の対策を脱臭装置だけに頼るのではなく多角的な視野で相乗効果を狙い出来る限り対策装置の低予算化を検討します。



STEP4 対策装置のデモテスト
選定した対策装置について実際の排気ガスを用いてデモテストを行い、効果検証を行います。
塗装工程、鋳造工程、ゴム混練りなど様々な工程がありますが、同じ工程でも臭気は複合ガスの為、設備や作業環境等により条件が異なります。
その為、臭気対策では実際の排ガスを用いてどれぐらい脱臭できるのかを試すことはとても重要です。
STEP5 対策装置の設置、運用
デモテストでの効果検証結果と拡散シミュレーションの結果を見比べて問題なさそうであれば実機製作に入ります。
弊社取扱の各設備の製作期間はおおよそ下記の通りです。
(あくまでも目安です)
・消臭剤スプレーシステム・・・約2~3ヶ月
・ハニカムフィルター(ゼオガイアフィルター)脱臭装置・・・約2~3ヶ月
・スクラバー排ガス洗浄装置・・・約5~6ヶ月
・充填式性炭脱臭装置・・・約5~6ヶ月
・触媒酸化式燃焼装置・・・約5~6ヶ月
*ご注文後設備の仕様承認を頂いてから現地に納品するまでの目安の日数です。
上記日数に試運転や効果測定は含まれませんのでご注意下さい。
特に弊社は原因調査から入りお客様の環境等々に合わせた形で設計するので
基本的にはオーダーメイドで設計・製作するんですね。
その為、標準で対応できるメーカーさんと比べると図面等の書類提出や設計後の納期も時間が掛かります。
ただ、お客様の使用条件に合わせた最適な設備設計が出来ます。(性能、運転条件、オペレーション、警報・インターロック、設置スペースなど)
どちらが良いかはお客様次第と思います。
STEP1からスタートしてSTEP5までで順当にいった場合に約1年~1年半ぐらい掛かるイメージです。

小風量~大風量まで幅広くカバー

排ガスを丸洗いする湿式脱臭装置

調理臭専門脱臭フィルター食品工場向き
対策完了までどれぐらい時間がかかるの?
上述のSTEP1(原因箇所の絞り込み)~STEP5(対策装置の設置、運用)まででだいたい1年~1年半ぐらいです。
対策完了までには少しお時間要しますが、適切な対策な為にはどれも必要なステップと考えています。
矢継ぎ早に進めるよりも着実に進めていった方が後々のトラブル回避につながります。